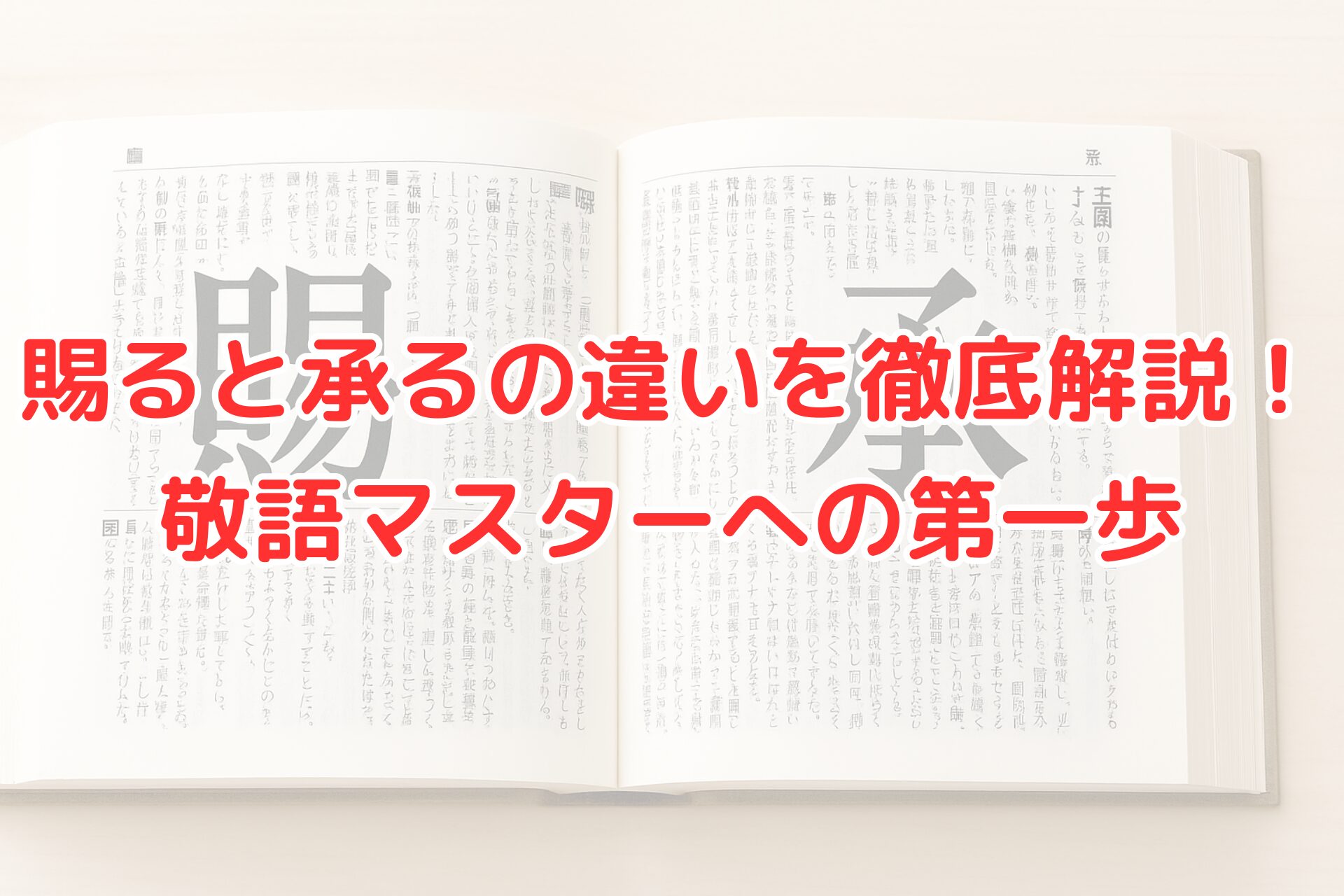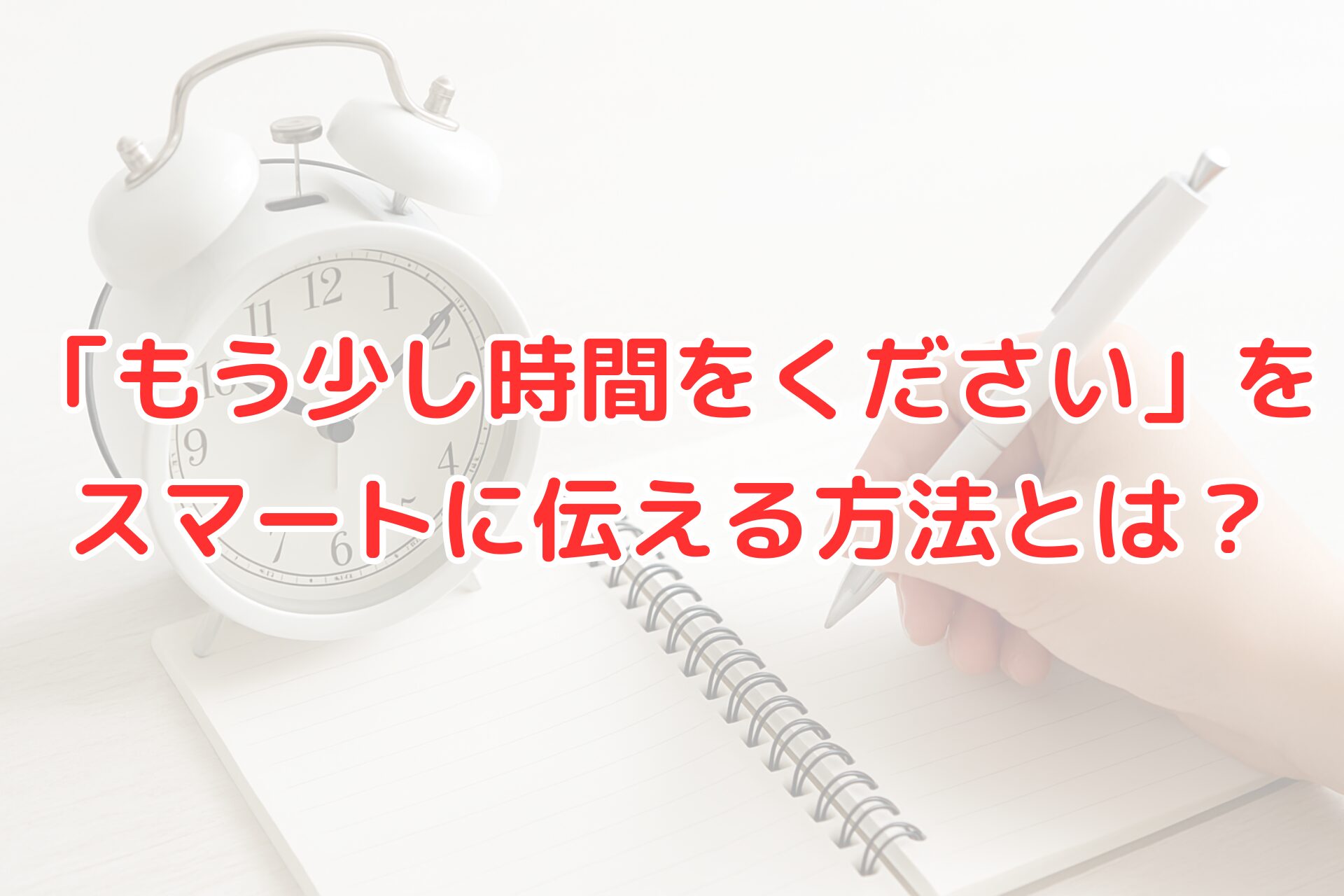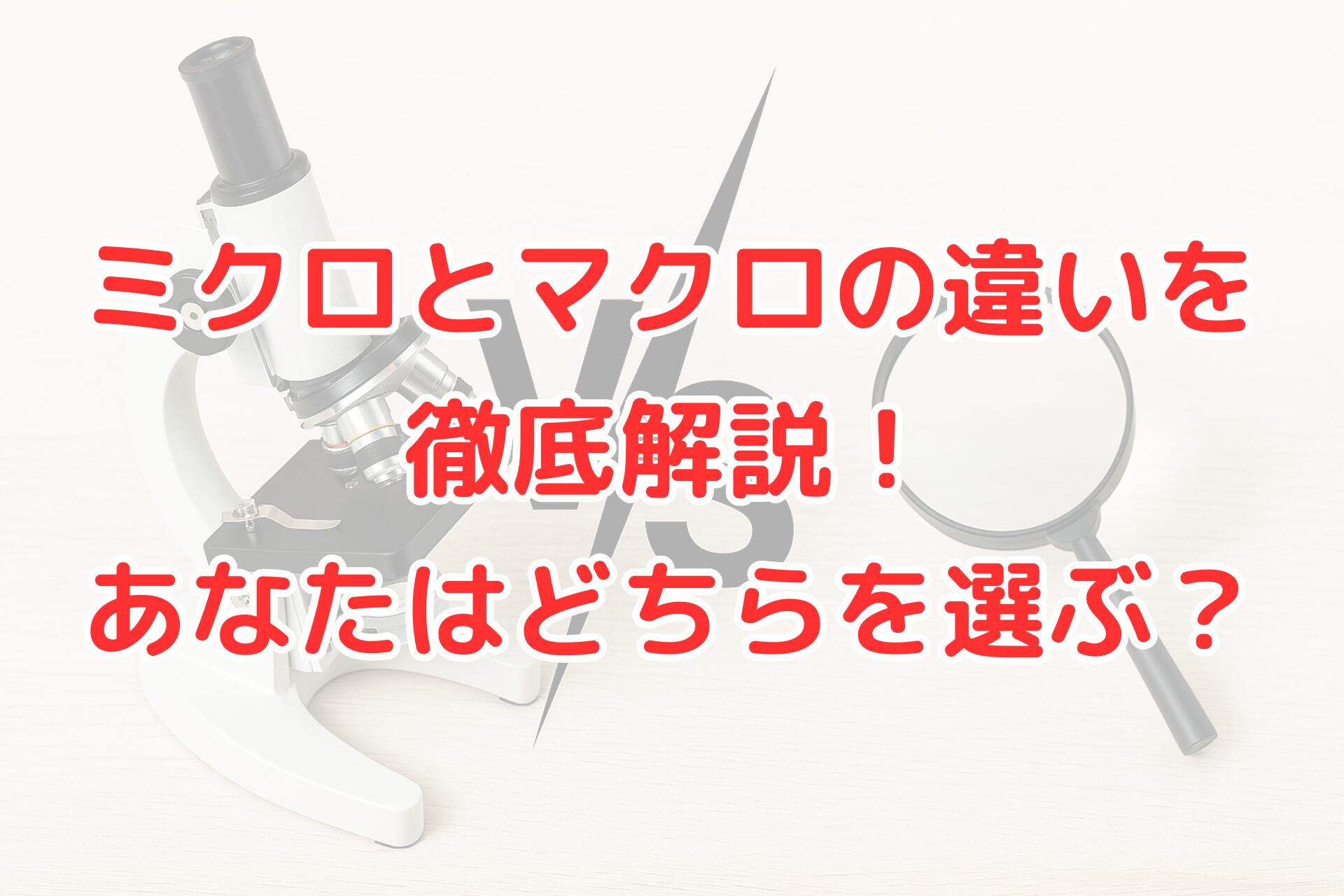ビジネスメールや会話で「賜る」「承る」という言葉を耳にするものの、使い分けに迷った経験はありませんか?
賜ると承るはどちらも敬語ですが、意味やニュアンス、使う場面が異なります。
この記事では、それぞれの意味と使い方、例文、類語を詳しく解説し、ビジネスシーンで自信を持って使い分けられるようになるためのポイントを紹介します。
※本記事の内容は一般的な敬語表現の解説です。
業界や企業ごとのルールによっては使い方が異なる場合がありますので、実際の利用時は所属組織の慣習やマニュアルもご確認ください。
はじめに:賜ると承るの重要性
敬語の基礎知識
敬語には「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の3種類があり、場面や相手によって使い分ける必要があります。
「賜る」と「承る」は、いずれも丁寧な印象を与える言葉ですが、敬語の種類や意味が異なるため正しく理解することが大切です。
さらに、現代ビジネスではメールやチャット、オンライン会議など多様なコミュニケーション手段が存在するため、状況に応じた敬語の使い分けが一層重要になっています。
誤用を避けるためにも、まずは基本を押さえることが第一歩です。
ビジネスシーンでの重要性
ビジネスメールや電話対応での敬語は、相手への敬意や信頼関係を示す重要な要素です。
誤った使い方をすると、失礼に受け取られる可能性があるため注意が必要です。
特に、社外のお客様や取引先に対しては、正しい敬語を使うことで会社全体の印象も左右します。
採用面接やプレゼンテーションなど、重要な場面で適切な敬語を使えると、あなた自身の評価も高まるでしょう。
また、社内でも上司や先輩への報告や相談において、適切な言葉遣いが円滑なコミュニケーションを生み出します。
検索意図と解決すべき課題
「賜ると承るの違い」で検索する人は、具体的な使い分けや適切な表現方法を知りたいと考えています。
中には「どちらをメールに使えばいいのかわからない」「電話でとっさに出てこない」という悩みを持つ人も多いでしょう。
本記事ではその疑問を解消し、実際のビジネスシーンですぐに活かせる知識と例文を提供します。
賜るの意味と使い方
賜るの意味
「賜る」は「いただく」の意味を持つ謙譲語です。
目上の人から何かをもらう、恩恵を受ける際に使います。
賜るの読み方と発音
読み方は「たまわる」です。
少し古風な響きがあり、改まった文章や式典、挨拶文などでよく用いられます。
賜るのビジネスシーンでの活用方法
感謝や依頼の文脈で使われることが多いです。
例えば「ご協力を賜りますようお願い申し上げます」は、依頼の際に非常に丁寧な表現です。
賜るの例文
- ご高配を賜り、誠にありがとうございます。
- ご意見を賜れれば幸いです。
- ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
- 本日は貴重なお時間を賜り、感謝申し上げます。
- ご厚情を賜りまして、心より御礼申し上げます。
賜るの言い換え表現
- いただく
- 受け取る
- 享受する(文章語)
承るの意味と使い方
承るの意味
「承る」は「聞く」「引き受ける」の意味を持つ謙譲語です。
相手からの依頼や話を謹んで受けることを表します。
承るの読み方と発音
読み方は「あずかる」ではなく「うけたまわる」です。
ビジネスメールや電話対応で頻繁に使われます。
承るのビジネスシーンでの活用方法
顧客対応や社外のやり取りで「承りました」と伝えると、丁寧かつ誠意ある印象を与えます。
承るの例文
- ご注文、確かに承りました。
- ご意見を承り、今後の改善に活かします。
- ご依頼の件、承っております。
- ご予約は明日10時で承っております。
- ご質問につきましても承りましたので、後ほど回答いたします。
承るの言い換え表現
- 受ける
- お聞きする
- お引き受けする
賜ると承るの違い
意味の違い
「賜る」は「もらう」「いただく」の意味で、物や行為を受ける際に使います。
「承る」は「聞く」「引き受ける」で、情報や依頼を受ける際に使います。
ここで重要なのは、単に語義だけでなく、相手との関係性や状況によりニュアンスが変わる点です。
例えば、表彰状をもらうときに「賜る」を使えば、厳粛さや感謝が強調されますし、顧客の要望を受けた時に「承る」を使えば、真摯な対応姿勢が伝わります。
謙譲語と尊敬語の違い
どちらも謙譲語ですが、対象が異なります。
「賜る」は相手からの恩恵に対してへりくだる表現、「承る」は自分が行為を引き受ける立場で使います。
さらに、尊敬語では「くださる」「おっしゃる」などが対応しますが、謙譲語はあくまで自分側のへりくだりを示します。
この違いを意識することで、過剰にへりくだり過ぎたり、逆に失礼になることを避けられます。
使用シーンの違い
- 賜る:感謝や依頼の表現に多用(例:式典の挨拶文、感謝状、お願いメール)
- 承る:注文・依頼・意見を受ける場面で多用(例:コールセンター対応、受注確認メール) また、会話では「承知しました」よりも丁寧に言いたいとき「承りました」を用いると好印象です。
注意点とマナー
「賜る」を軽い場面で多用すると不自然に感じられることがあります。
フォーマルな場面に限定して使うのが適切です。
さらに、「承る」はビジネスでよく使われますが、社内ではやや堅苦しい印象になる場合があるため、相手や状況を見極めることが重要です。
敬語の正しい使い分けに加えて、「ご安心ください」「お手数をおかけしますが」「念のためご確認ください」など、相手に気遣いを伝える表現を身につけておくと、柔らかく信頼される話し方になります。
賜ると承るの類語と表現
賜るの類語
- いただく:日常的に使えるもっとも一般的な表現で、メールでも会話でも幅広く活用可能。
- 拝受する(受け取る意を強調):文書やフォーマルな場面で用いられることが多く、特に契約書や公式文書に適しています。
- 享受する:文章語的な表現で、恩恵や利益を受けるニュアンスを強調できます。
- 受領する:ビジネス文書で受け取りを確認する際に使用されます。
承るの類語
- 伺う:訪問や意向を尋ねるときに使える便利な言葉。
- 拝聴する(聞く意を強調):セミナーや講演会などで相手の話を敬って聞くときに適切。
- お受けする:比較的柔らかい響きを持ち、カジュアルなビジネス会話にも馴染みます。
- 受け賜る:さらに丁寧に表現したいときに使用される重ね言葉。
相手に対する適切な表現
相手や状況に応じて言葉を選ぶことで、より丁寧かつ自然なコミュニケーションが可能になります。
例えば、重要なプレゼンや契約時には「拝受する」や「承る」を用いて重みを出し、日常的な社内連絡では「いただく」「受ける」などやや軽めの表現にすることでバランスが取れます。
シーン別に使い分けを意識することで、プロフェッショナルな印象を維持できます。
ビジネスシーンでの注意点
目上の人への使い方
相手への敬意を示すため、過剰に使いすぎず、文脈に合った表現を選びましょう。
特に、役職者や顧客に対しては、言葉遣い一つで印象が大きく変わります。
必要以上にへりくだると不自然になるため、程よい丁寧さを意識することが重要です。
例えば、感謝の意を伝える場合は「賜り」や「承り」を使いつつ、簡潔で分かりやすい文章を心がけましょう。
社内と社外の使い分け
社内ではややカジュアルな表現も許容されますが、社外では「賜る」「承る」などを積極的に使うことで、丁寧さを演出できます。
社外メールでは挨拶文や結びの言葉にも気を配り、「今後ともご指導ご鞭撻のほど賜りますようお願い申し上げます」など定型句を効果的に使うと印象が良くなります。
逆に社内では、効率重視で「承知しました」や「了解です」など、少し柔らかい表現にすることでスムーズなコミュニケーションが図れます。
コミュニケーションの印象
適切な敬語の使い分けは、信頼関係の構築に直結します。
一度身につければ、長期的に好印象を与え続けることができます。
さらに、正しい言葉遣いは相手へのリスペクトだけでなく、自分の自信や説得力にもつながります。
会議や商談の場で適切に使い分けられると、プロフェッショナルとしての評価が高まり、結果として良好な人間関係やビジネスチャンスの拡大にも寄与します。
まとめ:敬語マスターへの第一歩
重要なポイントの再確認
- 「賜る」は「いただく」。特に感謝や依頼の場面で使うと相手に丁寧さが伝わる。
- 「承る」は「聞く・引き受ける」。依頼や注文、意見を受ける際に最適。
- フォーマルな場面で適切に使い分けることが、あなたの印象を大きく左右する。
- 状況や相手の立場を考慮して表現を変えると、より柔軟なコミュニケーションが可能。
実生活での活用方法
メールや会話で意識的に使い分けることで、自然と身につきます。
練習を重ねるとスムーズに使えるようになります。
たとえば、社内では「承知しました」を使いつつ、社外では「承りました」と言い換える練習をすると、場面に応じた自然な言葉遣いが身につきます。
ロールプレイや実際のやりとりを振り返る習慣をつけると、さらに定着が早まります。
敬語の学びを深めるために
他の敬語表現も合わせて学ぶと、さらに表現の幅が広がります。
関連書籍やオンライン講座で体系的に学ぶのもおすすめです。
職場で先輩の言葉遣いを観察する、ドラマやニュース番組の敬語表現に注目するなど、日常の中で学べる機会は多くあります。
敬語を制することは、ビジネスコミュニケーションを制することにつながります。
正しい敬語を使える人は、信頼を得やすく、仕事のチャンスも広がります。