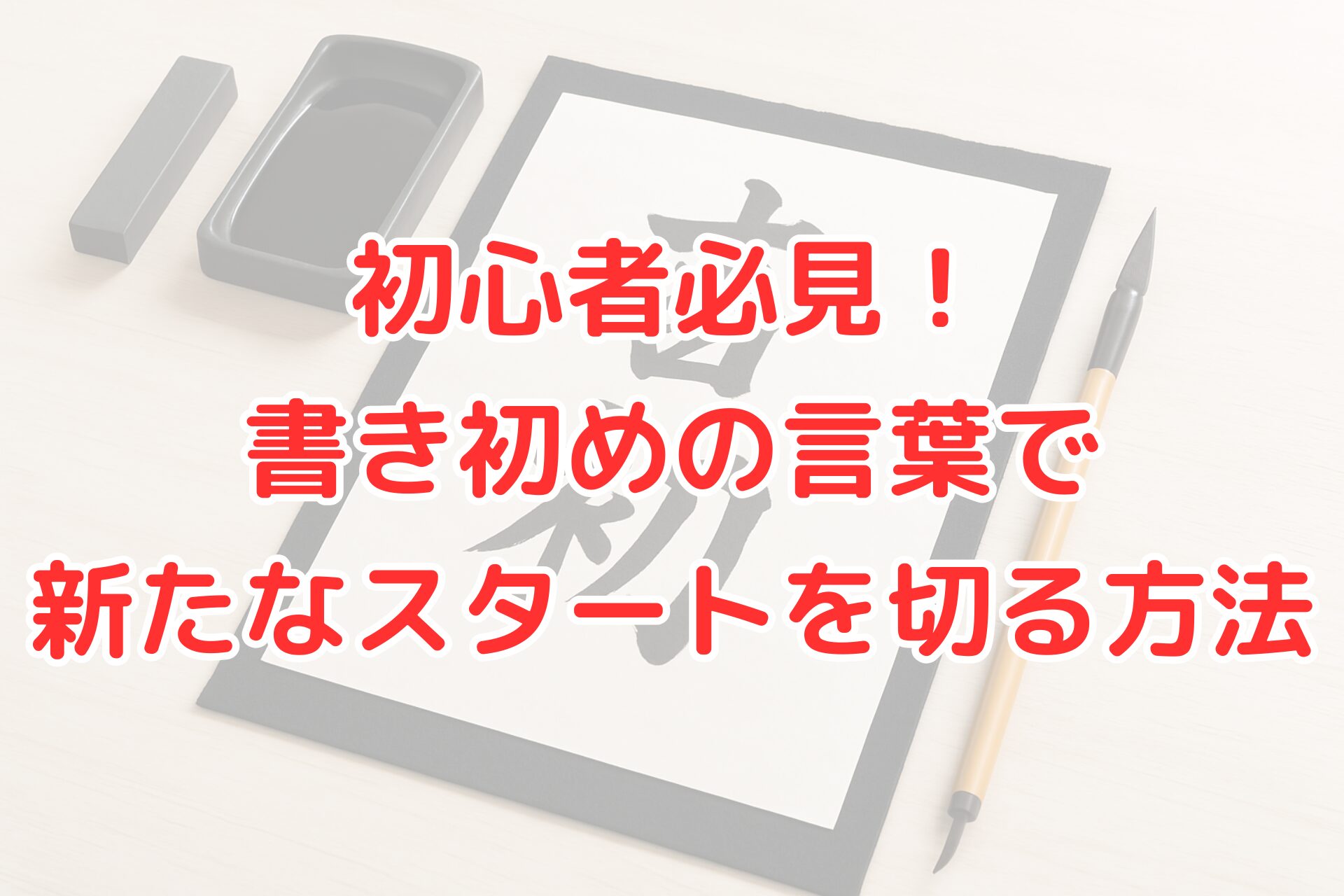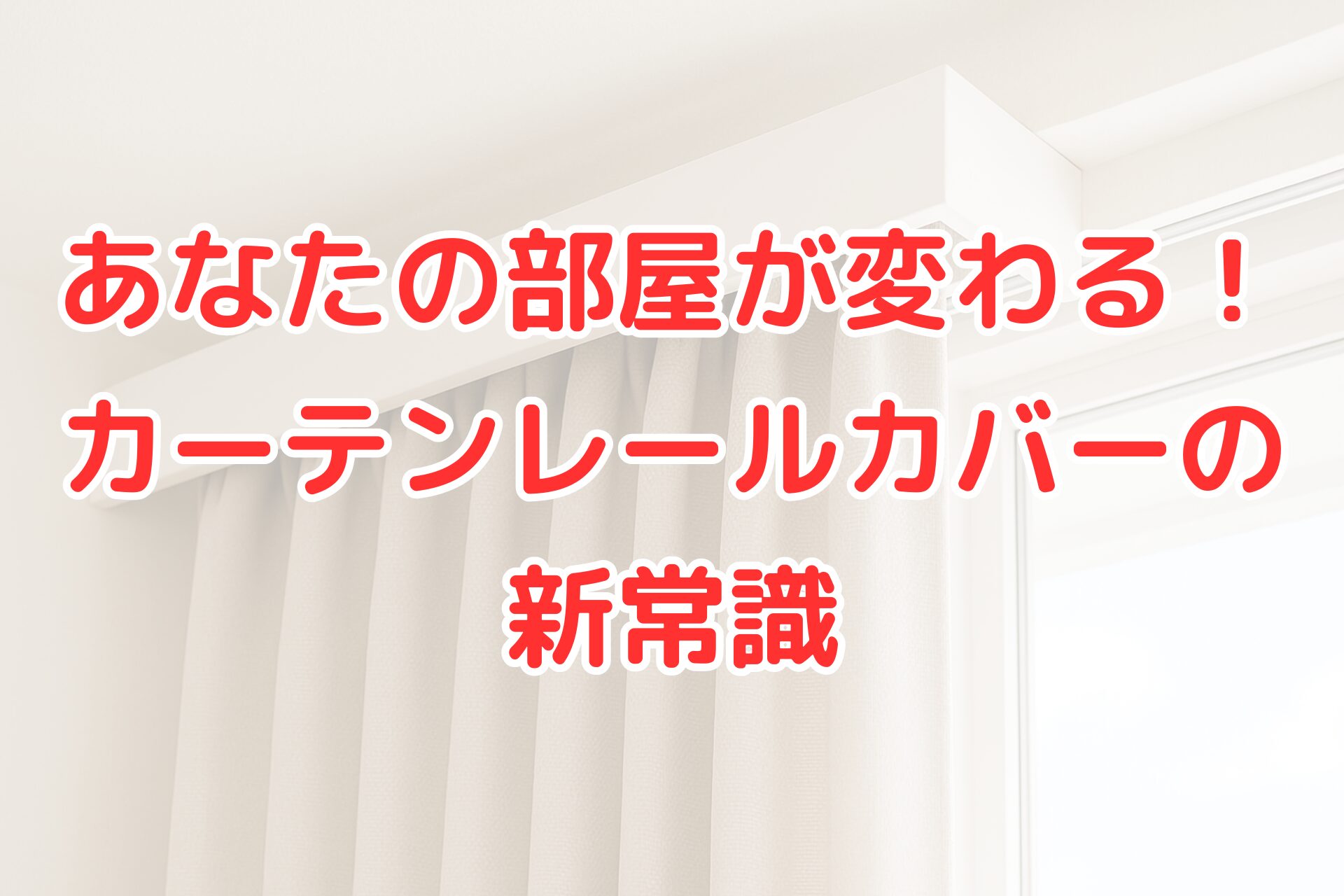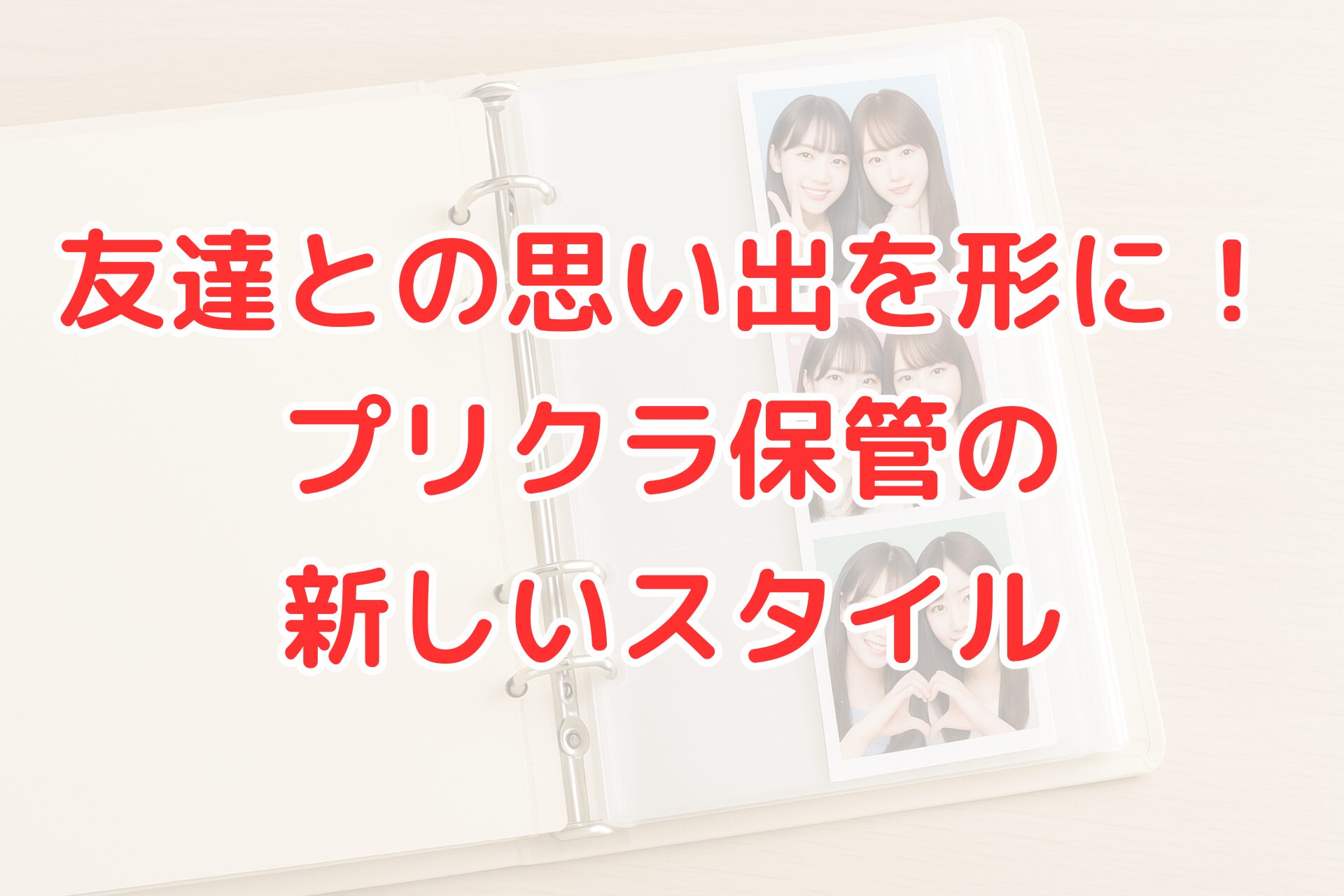新しい年の始まりに心を整え、前向きな気持ちでスタートを切る「書き初め」。
一年の抱負や願いを筆に託すこの行事は、ただの習慣ではなく、自分の心と向き合う大切な時間です。
この記事では、「書き初めの言葉」選びのコツやおすすめの言葉、そして上手に書くための準備やコツを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。
「今年こそは新しい自分になりたい」「心を整えて一年を始めたい」というあなたにぴったりの内容です。
※注意:墨や筆を使う際は、机や床にインクがつかないように新聞紙やシートを敷いておくと安心です。
小さなお子さんと一緒に行う場合は、汚れてもいい服装を選びましょう。
初心者が知っておくべき書き初めの基本
書き初めとは?その歴史と由来
「書き初め(かきぞめ)」は、新年の1月2日に初めて筆を取って文字や詩を書く日本の伝統行事です。
その起源は古く、平安時代にさかのぼります。
当時の貴族たちは、年の初めに縁起の良い方向(恵方)に向かって詩や歌を書き、学問や書の上達を祈願していました。
やがて江戸時代には庶民にも広まり、学校や家庭で行われるようになりました。
今日では、「心を整え、抱負を文字にすることで自分を見つめ直す」という意味が込められ、学校の冬休みの宿題としても定着しています。
また、書き初めは「新しい一年の第一歩」として、清らかな気持ちで物事に取り組む儀式として大切にされています。
書き初めが持つ意味とは?
書き初めには、単なる「書道の練習」以上の意味があります。
それは、「心に描いた目標や願いを形にする」こと。
文字には不思議な力があり、書くことでその言葉が自分の潜在意識に刻まれ、行動の原動力になります。
たとえば「努力」や「挑戦」と書けば、自然とその意識が芽生え、日々の選択にも影響を与えます。
つまり、書き初めは「言葉を通じた自己宣言」のようなもの。
「こうなりたい」「こう生きたい」という気持ちを、筆に込めて書くことで、自分自身の背中を押すのです。
書き初めを通じた新年の抱負
年始に書く言葉は、一年を象徴するテーマです。
「笑顔」「健康」「努力」「飛躍」など、シンプルな言葉でもかまいません。
大切なのは、「今年の自分をどうありたいか」を素直に表すこと。
また、「感謝」「思いやり」など、他者との関係を意識した言葉も人気です。
自分の内面とじっくり向き合うことで、書くべき言葉が自然と見えてくるはずです。
書き初めにおすすめの言葉
美しい言葉の選び方
書き初めに選ぶ言葉は、「響きの美しさ」と「意味の深さ」がポイントです。
例えば以下のような言葉は、心が引き締まる美しさを持っています。
- 希望:前向きに未来を描く力をくれる言葉。
- 感謝:日常の幸せを大切にできる心を表します。
- 誠実:自分にも他人にも嘘をつかず、真っ直ぐに生きる姿勢。
- 光明:明るい未来や希望の象徴。
- 飛翔:さらなる成長を願う言葉。
どの言葉も、筆で書くと形が映え、美しい印象を与えます。
また、「静心」「和敬」「清風」などの古風な言葉も、品のある雰囲気を演出してくれます。
書き初めの言葉を選ぶときは、『めでたい』の意味のように、前向きで縁起の良い言葉を意識すると素敵です。
面白い書き初め言葉の紹介
近年では、ユーモアのある書き初めも人気です。
たとえば子どもたちの間では、「宿題早く終わらせる」「お菓子控える」など、ちょっと笑える抱負も見られます。
大人でも「笑顔増やす」「マイペース」「焦らない」など、肩の力を抜いた言葉もおすすめ。
大切なのは、自分らしさが表れているかどうかです。
「真面目な言葉じゃないといけない」と思い込まず、心が温かくなる言葉を選びましょう。
大人と小学生に適した書き初め言葉
年齢や立場によって、書くべき言葉も変わってきます。
小学生におすすめ
- 元気
- 友情
- 笑顔
- 夢
- 努力
- がんばる
これらの言葉は、学校生活の目標にもつながりやすく、書きやすいのもポイントです。
大人におすすめ
- 挑戦
- 飛躍
- 感謝
- 自立
- 成長
- 調和
大人になると、生活や仕事、家族など、いろいろな側面があります。
自分が一番大切にしたい価値観を、言葉にしてみましょう。
四字熟語で表現する書き初め
少し上級者向けですが、四字熟語も人気です。
文字数が多い分、意味が深く、力強い印象を与えます。
- 一念発起(いちねんほっき):強い決意をもって行動すること。
- 初志貫徹(しょしかんてつ):最初の志を貫く。
- 感謝報恩(かんしゃほうおん):感謝の気持ちを忘れずに恩に報いる。
- 有言実行(ゆうげんじっこう):言葉にしたことを実際に行う。
- 心機一転(しんきいってん):新しい気持ちで再出発する。
自分の抱負を四字熟語にすると、より引き締まった印象になります。
書き初めを成功させるための準備
書道に必要な道具とその使い方
書き初めを行うには、次の道具を用意しましょう。
- 筆:大筆・小筆の2種類があると便利。
- 墨:液体墨(墨汁)がおすすめ。
- 硯:墨を入れる器。
- 半紙:文字を書く紙。
- 下敷き:机が汚れないように。
- 文鎮:紙を押さえる重り。
- 新聞紙・シート:床や机を守るため。
使う前に、筆の先を整えることが大切です。
新品の筆は糊がついているので、ぬるま湯でほぐしてから使いましょう。
書き初めで使う毛筆と半紙の選び方
筆は、太さと弾力が重要です。
初心者には、中サイズの柔らかめの筆が扱いやすいでしょう。
半紙は、少し厚めでにじみにくいものを選ぶと失敗が少なくなります。
また、書きたい文字の大きさに合わせて、紙のサイズも選びましょう。
「大きくのびのび書くこと」が上達の近道です。
挑戦する前に知っておきたいこと
書き初めは、ただ書くだけではなく、心の準備も大切です。
深呼吸をして心を落ち着かせ、姿勢を正してから筆を取ります。
そして、「この一文字に思いを込める」という意識を持つことで、自然と丁寧な字になります。
書き初めの方法とステップ
一般的な書き方とバランスの取り方
書き初めは、構図のバランスが美しさを左右します。
縦書きの場合、中心線を意識し、文字の間隔を均等に保ちましょう。
特に、一番上の文字を少し大きめに書くと安定感が出ます。
また、筆の入り方・止め方・払い方を意識して、ゆっくりと筆を運ぶこと。
焦らず、「一筆一筆を丁寧に」が基本です。
新年の書き初めを楽しくするコツ
音楽を流したり、家族と一緒にお菓子を用意したりして、楽しめる雰囲気づくりをすると、書くことがもっと好きになります。
また、数枚練習してから本番に挑むと、緊張も和らぎます。
大切なのは、「上手く書くこと」よりも「心を込めること」です。
家族で楽しむ書き初めの方法
家族で書き初めをするのもおすすめです。
それぞれが「今年の抱負」を書き、見せ合うことで、お互いの目標を応援し合うきっかけにもなります。
お子さんの作品は飾ると喜びも倍増します。
書き初めを振り返る
どんと焼きでの作品を飾ろう
書き初めは、どんと焼き(1月15日前後)で燃やすと字が上達するという風習があります。
神社や地域の行事で行われることが多いので、ぜひ参加してみましょう。
炎に願いを託すことで、気持ちの切り替えにもなります。
書き初めを継続する方法と上達のポイント
書き初めを年に一度の行事で終わらせず、毎月一枚書く習慣をつけると、驚くほど上達します。
書いた作品をファイルにまとめておくと、自分の成長も実感できます。
書き初めを通じた自身の成長の記録
最初はうまく書けなくても大丈夫。
大切なのは、続けることと気持ちを込めること。
一年後、振り返ったときに「成長したな」と感じられることが、最大の喜びです。
まとめ
書き初めは、一年のスタートを象徴する心の儀式です。
選ぶ言葉には、自分の想いや目標を込めてください。
上手さよりも、心を込めて書くことが大切。
「今年も頑張ろう」と思える一枚を、あなたの手で生み出してみてください。